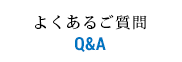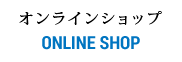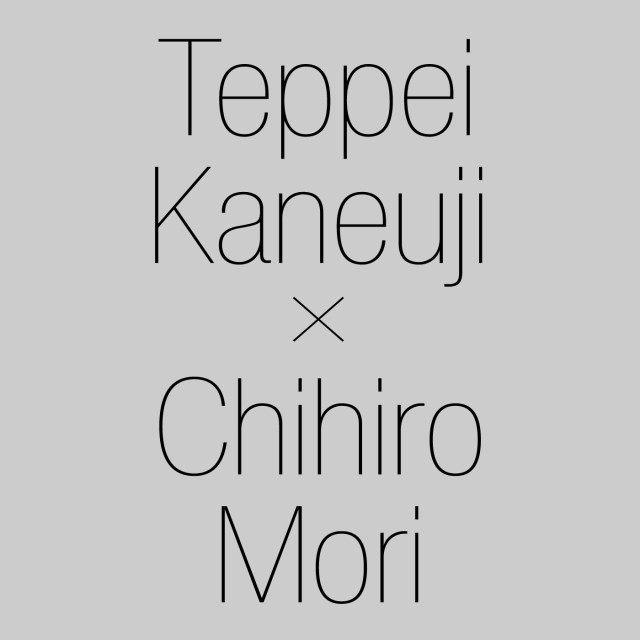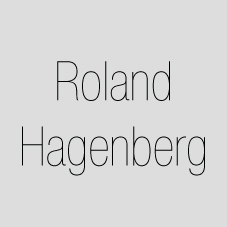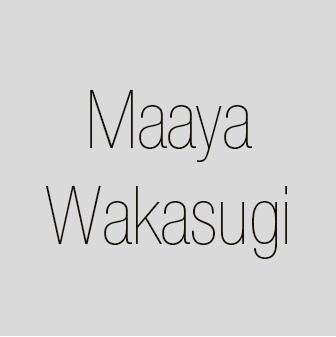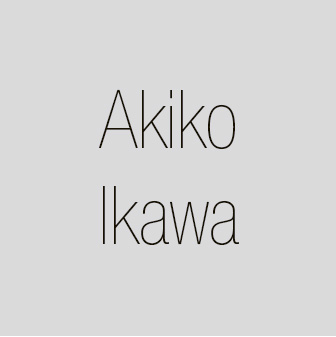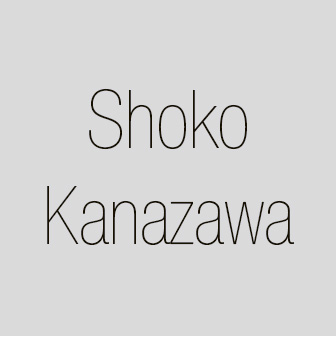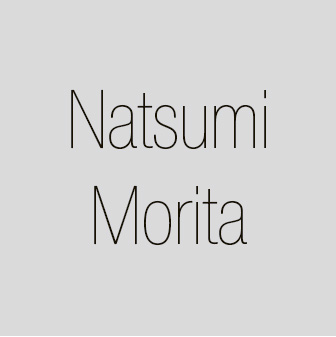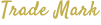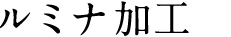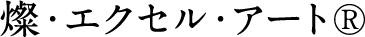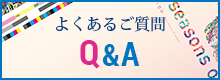Recommendedおすすめ商品
-
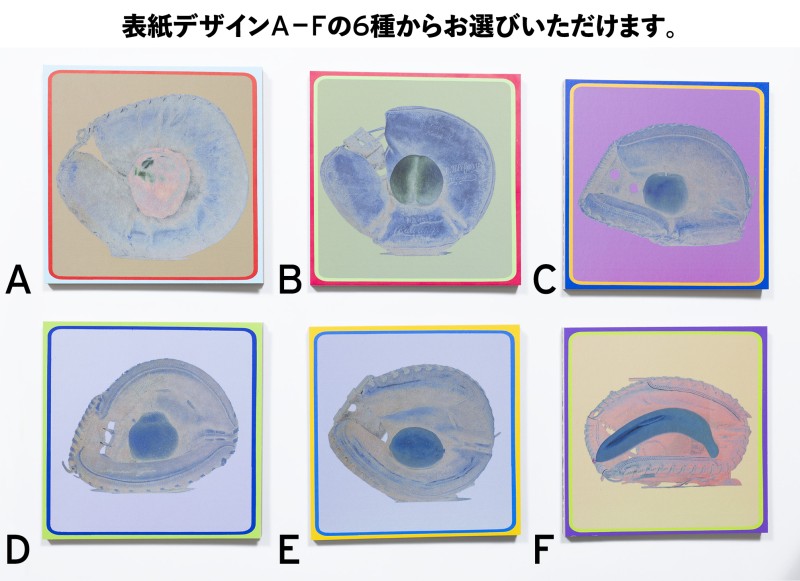
「⾦⽒徹平 森千裕」展カタログ
¥55,000(税込)
-
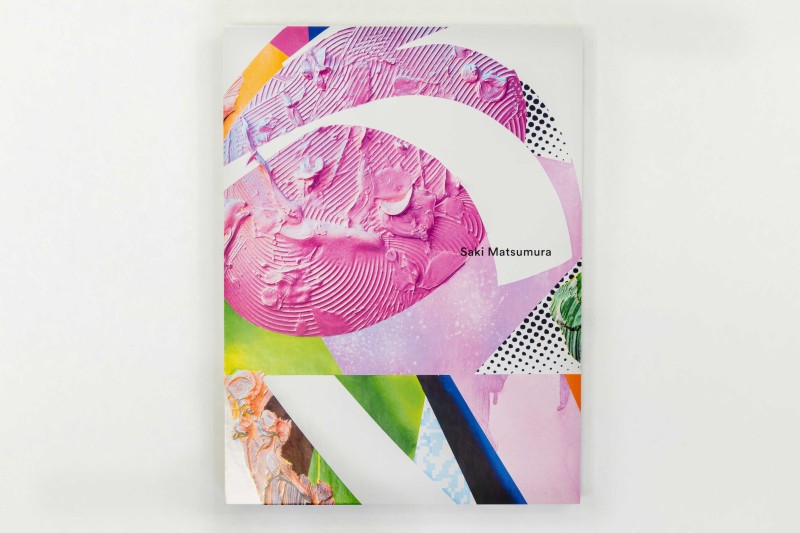
松村咲希 作品集
¥3,500(税込)
-
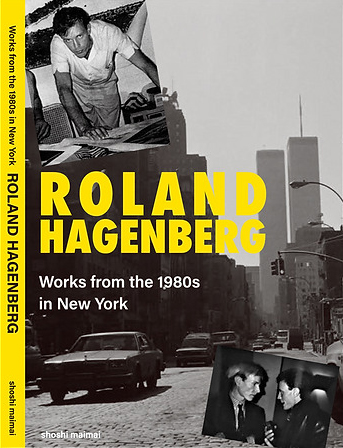
Works from the 1980s in New York_Roland Hagenberg
¥3,520(税込)
-
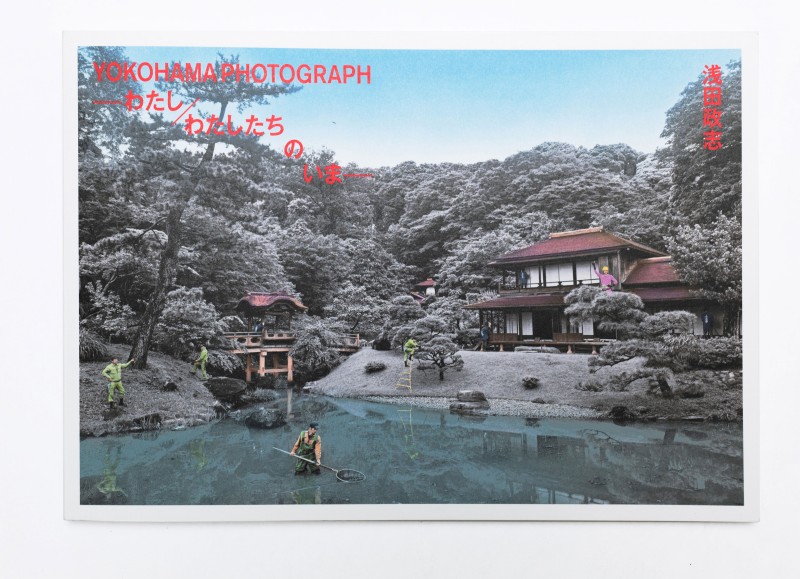
KAAT EXHIBITION 2023 浅田政志 展 YOKOHAMA PHOTOGRAPH -わたし/わたしたちのいま- カタログ
¥2,500(税込)
-

花より男子展 -Jewelry BOX- 一筆箋1
¥440(税込)
-
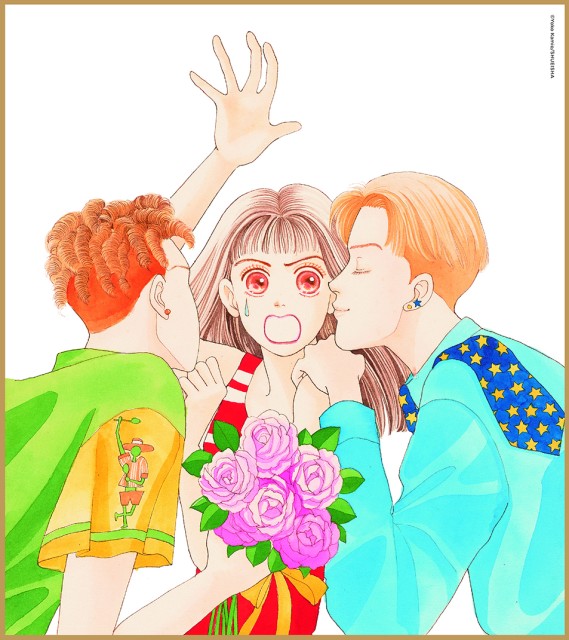
花より男子展 -Jewelry BOX- 色紙1
¥1,650(税込)
-
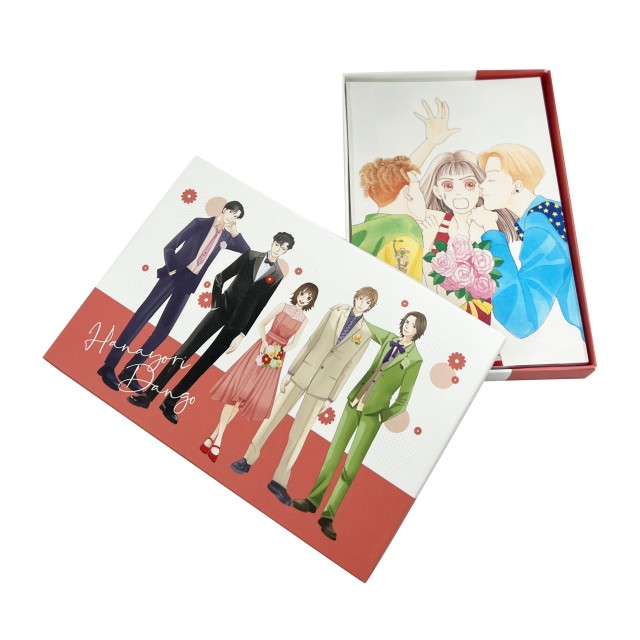
花より男子展 -Jewelry BOX- ポストカードセット
¥3,520(税込)
-
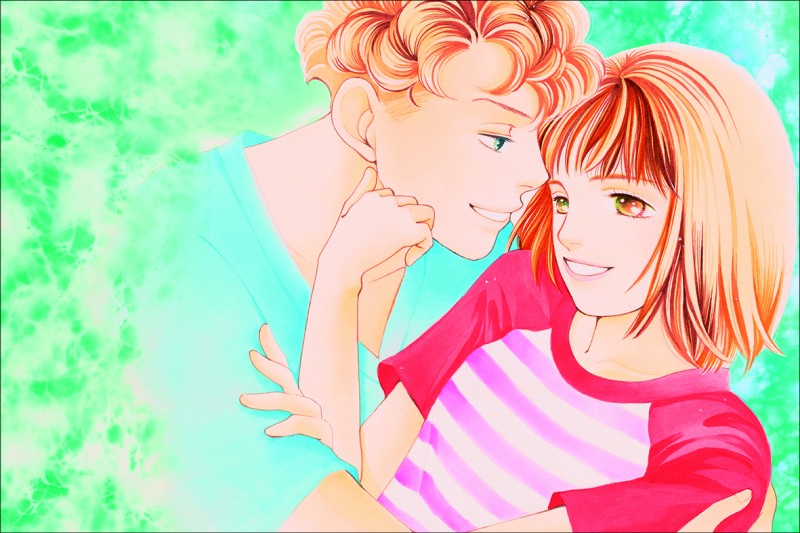
花より男子展 -Jewelry BOX- ポストカード12
¥154(税込)